こんにちは。内科クリニックで働く看護師のトトです。
日々、患者さんと関わる中で“睡眠不足”に悩む方は多いと感じています。
「眠っているのに疲れが取れない」
「夜中に目が覚めて、その後眠れない」
「寝付きが悪い」
などなど。
ということで今回、“質の良い眠り”を得るためにポイントをご紹介します。
快眠習慣のポイント
体内時計を整える
体内時計とは、1日約24時間の周期で働く体の“時間調整機能”のことをいいます。
これは、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という場所で管理されていて、
睡眠・覚醒・ホルモン分泌・体温・血圧・代謝など、ほぼ全ての生命活動に関わっています。
◆体内時計を整える3つの基本
1.朝決まった時間に起きて「朝日を浴びる」
太陽の光が、脳の視交叉上核に「朝が来たよ」と伝えてくれます。
これで体内時計がリセットされ、夜に自然と眠気が来るようになります。
2.毎日同じ時間に寝て・起きる
平日と休日の睡眠時間差を最小限にするとこで、リズムが崩れにくくなります。
3.朝食をしっかり食べる
食事も体内時計に影響します。
特に「朝のたんぱく質」は、日中の代謝とホルモン分泌をサポートします。
就寝90分前の入浴で深部体温をコントロールする
深部体温とは、体の中心部(脳や内蔵など)の温度のことで、私たちの眠気にはこの深部体温の変化が深く関わっています。
Q:なぜ「90分前の入浴」が効果的なの?
A1:お風呂で一時的に深部温度を上げる
38〜40度のお湯に15〜20分低度浸かると、体の奥の温度(深部温度)がゆっくり上昇します。
A2:入浴後、時間をかけて深部温度が下がる
お風呂から出たあと、皮膚から熱が放散され、90分程かけて温度が下がります。
この「下降」のタイミングが、脳に「そろそろ寝よう」と合図を出します。
睡眠環境を整える
眠るためには、脳と体が「安心」し、リラックスできる環境が必要です。
光・音・温度・湿度・寝具・香りなどの物理的な要因が不快だと、
自律神経が交感神経(緊張モード)が優位になり、眠りが浅くなったり、中途覚醒しやすくなります。
◆睡眠環境を整えることで得られる効果
1.寝付きが早くなる
部屋の明るさや音、温度が快適になることで、入眠までの時間が短縮する。
2.中途覚醒が減る
不快な刺激(暑さ・寒さ・音など)がなくなると、夜中に目覚める回数が減少する。
3.深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間が増える
静かで暗く、体が冷えすぎず、適度な湿度がある環境では、脳も「安全だ」と判断して深く眠れるようになります。
スマホと距離をとる
スマホが睡眠を妨げる3つの理由
1.ブルーライトがメラトニンの分泌を抑える
スマホやタブレット、パソコンなどの画面からは「ブルーライト」が出ています。
この光は昼間の太陽光に似た性質を持ち、脳を「今は昼間」と錯覚させてしまいます。
その結果、眠気を促す「メラトニン」の分泌が減り、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。
2.情報刺激で脳が覚醒する
SNS、動画、ニュースなど、寝る前にスマホで情報をたくさん取り込むと、
脳が興奮してしまい、副交感神経(リラックスモード)に切り替わらなくなります。
3.時間を奪われて「ついつい夜ふかし」
寝る前にスマホを触り始めて、気づいたら30分、1時間経っていた…
そんな経験ありませんか?これは「ドーパミン報酬回路」が刺激されることで、
“もっと見たい”が止まらなくなる仕組みになっているからです。
その結果、睡眠時間が削られ、翌日のパフォーマンス低下に直結します。
カフェインとアルコールは控えめにする
◆カフェイン
カフェインには「アデノシン受容体」をブロックする作用があります。“アデノシン”とは、脳に“疲れ”を知らせ、眠気を引き起こす物質です。カフェインを摂ると、この働きが妨げられてしまい、「本当は眠いはずなのに、眠気を感じなくなる」のです。
影響時間は、個人差はありますが、摂取後4〜7時間ほど効果が続きます。
◆アルコール
アルコールは一見、リラックス作用があり「寝付きはよくなる」ように感じます。しかし、実際にはノンレム睡眠を妨げ、夜中に何度も目覚めやすくなります。
さらに、利尿作用により夜中にトイレで起きやすくなったり、脱水による喉の渇き・頭痛を引き起こすこともあります。
睡眠薬の代わりに飲酒する方もいますが、習慣化すると“依存”につながるリスクもあるので注意が必要です。
軽いストレッチや呼吸法を取り入れる
スムーズな眠りにつくためには、交感神経から副交感神経への切り替えが必要です。
ストレッチや呼吸法は、この自律神経のバランスを整えて、心と体を「おやすみモード」へ導く自然なスイッチになります。
◆軽いストレッチの効果
1.血流改善
日中に凝った筋肉(特に首・肩・腰)を伸ばすことで、
血流が良くなり、冷えや凝りが緩和されます。
2.副交感神経が優位になる
ゆっくりした動きは緊張をほぐし、自律神経の切り替えをスムーズにします。
特に寝る前の背中・股関節・ふくらはぎを伸ばすと、深いリラックス効果があります。
3.深部体温が下がりやすくなる
軽い運動後の体温上昇とその後の緩やかな下降が、入眠を助けます。
◆呼吸法の効果
1.自律神経のバランスを整える
ゆっくりした腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、リラックス状態をつくります。
2.心拍が落ち着き、不安感も減る
心拍数や血圧が下がるため、「眠れないかも…」という焦りや不安も自然と和らぎます。
まとめ
睡眠は「心と体の治療時間」です。少しの工夫で、ぐっすり眠れる夜がぐんと増えるかもしれません。
忙しい日々の中でも、自分の体をいたわる時間をぜひ大切にしてください。
明日も元気に生きられますように。
ご精読ありがとうございました。

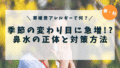

コメント