こんにちは。内科クリニックで働く看護師のトトです。
季節の変わり目になると、くしゃみや鼻水、頭がぼーっとする…
といった症状がでることはありませんか?
もしかすると、それ、「寒暖差アレルギー」かもしれません。
正式には「アレルギー」ではなく気温差などによる自律神経の乱れから起こる症状で、
多くの人が悩まされてる季節の変わり目に出やすい不調の一つですね。
ということで今回、この寒暖差アレルギーの正体と日常でできる対策についてご紹介します。
寒暖差アレルギー
寒暖差アレルギーとは?
寒暖差アレルギーは、医学的に「血管運動性鼻炎」と呼ばれます。
気温差(7度以上がでやすい)によって自律神経が乱れ、鼻の粘膜が過剰反応してしまうことです。
症状は以下のようなものがあります。
・透明で水っぽい鼻水が出る
・鼻づまりやくしゃみが止まらない
・頭が重い、ぼーっとする
・朝や外出直後に特に症状が強くでる
・目のかゆみ・発熱はない
など、風邪の症状に似ているのが特徴です。
寒暖差アレルギーが起こるメカニズムは?
私たちの体は、気温の変化に応じて血管を広げたり縮めたりして、体温を一定に保っています。この調整をしているのが「自律神経」です。
ところが、朝晩の寒暖差が激しい日や、冷暖房の効いた室内外を行き来する日が続くと、自律神経が混乱し、鼻粘膜の血管が過剰に反応=鼻水・鼻づまりが起こります。
寒暖差アレルギーが起きやすい状況は?
寒暖差アレルギーが起きやすいのは以下のようなシーンが多いです。
・朝晩と日中の気温差が激しい春や秋
・暖房、冷房で室内外の温度差が大きい
・お風呂と脱衣所で温度差がある
・外出と帰宅を繰り返す日
など
予防&対策
寒暖差アレルギーの予防と対策は以下の通りです。
◆体温調節をこまめに行う
・薄手の上着やストールで、気温差にすぐ対応できるようにする
・首、手首、足首を冷やさないようにする
◆自律神経を整える生活を心がける
・起床、就寝時間を一定にする
・湯船にゆっくりつかる(38〜40度のお湯がおすすめ)
・スマホやPCは寝る1時間前までにして、睡眠の質を向上させる
◆腸内環境の改善も有効
・発酵食品(納豆、味噌、ヨーグルトなど)を積極的に摂取する
・食物繊維と水分をしっかり摂って、腸内環境から免疫力をサポートする
まとめ
寒暖差アレルギーは、見過ごされがちですが「自律神経からのサイン」です。
体から出るサインを無視せず、日々の生活で少しずつ予防・改善を心掛けることが大切です。
セルフケアで改善しない場合は、耳鼻科や内科の受診をおすすめします。特に花粉症との見分けがつきにくい時期(春や秋)は早めの受診をおすすめします。
明日も元気に生きられますように。
ご精読ありがとうございました。
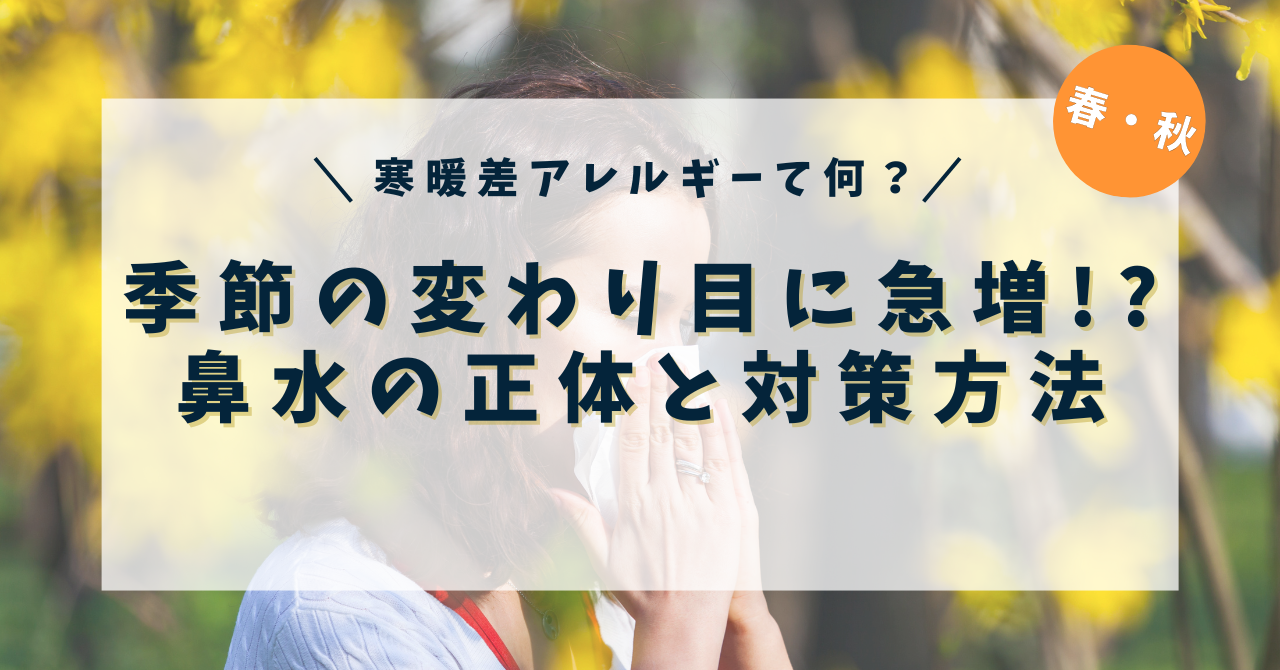


コメント