こんにちは。内科クリニックに勤務する看護師のトトです。
先日、高血圧症のAさんから
「友達から太ってるのは果物食べ過ぎだからって言われたの。果物ってダメなの?」
と質問されました。
果物は朝食や食後のデザートに食べることが多いですね。
ビタミンや食物繊維が豊富なので健康のために食べてるという方多いと思います。
定期的な食事指導をしているAさんの食生活は特に乱れてもおらず、むしろジムにも通っているにも関わらず体重は少し増加していました・・・
ということで、今回は!
「果物」は体重増加に原因になるのかについて説明します。
果物の代表的な栄養素
ビタミンC
ヒトは体内でビタミンCを作ることができないため、食品や食事などで摂取する必要があります。
ビタミンCは免疫力を高め、肌を健康に保ちます。
不足すると怠さや筋力低下、怒りっぽくなる、体重減少、筋肉や関節の痛みなどがあります。
過剰に摂取すると腹痛や下痢などの胃腸障害を引き起こすことがあります。
カリウム
ミネラルであるカリウムは、血圧の調整や浮腫みの予防になります。カリウムを十分に摂取すると、
ナトリム(塩分)の過剰摂取によって引き起こる高血圧の予防や改善に効果があります。
不足すると食欲不振や筋力低下、不整脈などの症状が現れます。健康な人の場合、過剰に摂取しても血中のカリウム濃度は一定に保たれるので、過剰症状は起こらないと考えられています。
食物繊維
食物繊維は便通を助けて、腸内環境を整えます。
果物の食物繊維は水溶性(便のカサを増やす)と不溶性(便を柔らかくする)の両方を含んでいます。
ポリフェノール
ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化を予防します。
活性酸素やフリーラジカルによる酸化を防ぐ効果があります。
果糖とは?
甘さについて
果糖(フルクトース)は、単糖類(それ以上分解できない糖質)に分類される糖質のことで、果物や蜂蜜などに含まれています。甘味度は、サトウキビやテンサイに多く含まれている「スクロース」を“1”とすると果糖は“1.73”で、天然の糖の中で最も甘く、冷やすとさらに甘みを感じやすいです。
代謝について
果糖は、小腸で吸収されて主に肝臓で代謝されます。“ブドウ糖”に変換されるか、中性脂肪の合成に利用されます。果糖は血糖値を直接上げることはありませんが、、過剰に摂取すると“中性脂肪”に変わりやすいです。
1日あたりの果物摂取量は?
適量摂取量
果物の適量摂取量は、健康な成人の場合、1日約200g※が目安とされています。
例えば、
□みかん:2個
□りんご:1個
□バナナ:2本
□柿:1個
□キウイ:1個
□いちご:約6粒
□グレープフルーツ:半分
※これらは可食部の重量です!
果糖の量を角砂糖に換算したら?
角砂糖1個=糖質4gとしたら・・・
□みかん:2個 ▶約6個(約90kcal)
□りんご:1個 ▶約9個(約140kcal)
□バナナ:2本 ▶約11個(約170kcal)
□柿:1個 ▶約7個(約120kcal)
□キウイ:1個 ▶約3個(約53kcal)
□いちご:約6粒 ▶約2個(約44kcal)
□グレープフルーツ:半分 ▶約3個(約57kcal)
結論
果物は生活習慣病や美容効果が期待できる、栄養豊富の食品です。
果糖により効率的にエネルギーが補給でき、疲労回復にも効果的です。
抗酸化作用もある栄養素によって老化防止や美肌効果を期待できます。
ですが、適量(一日200g程度)にする必要があります。
果糖を過剰に摂取してしまうと高トリグリセリド血症や高コレステロール血症、内蔵脂肪などにつながる恐れがあります。また、夜間に果物を食べると糖分が脂質として蓄積されやすくなる場合があります。
果物は適量を守り、新鮮な生の状態で摂取することで健康効果を最大限に引き出すことができます。
できるだけ、起床後から活動時間内に食べるようにして、摂ったエネルギーが脂肪として体に溜めないようにしましょう。
明日も元気に生きられますように。
ご精読、ありがとうございました。


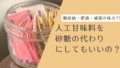
コメント