こんにちは。看護師のトトです。
“腎臓”は、血液をキレイにして体のバランスを保つ大切な臓器です。
高血圧はその大切な腎臓にダメージを与える大きな原因の一つですが・・・
実は、「血圧が低すぎることがリスク」になることがあります。
血圧管理は、病気によって「高すぎず、低すぎず」で管理することが大切な場合があります。
ということで今回は、「腎臓と血圧」の関係についてご紹介します。
腎臓と血圧管理
腎臓と血圧の関係
✅️腎臓は1日150リットルの血液をろ過しています。
✅️ろ過機能を働かせるには、「ある程度の血圧」が必要になる場合があります。
✅️腎臓には、糸球体といわれる細かい血管が集まっていて、
そこにかかる圧力で老廃物や余分な水分を尿として排出しています。
✅️血圧が安定しないと、この「ろ過機能」がうまく働かなくなる場合があります。
高血圧が腎臓に与える影響
✅️長期間の高血圧は、腎臓の血管を硬くしたり、狭くしたり、ろ過機能を低下させる原因になります。
✅️そうすると、「糸球体」が「無理に働きすぎる」状態になり、腎臓の機能が低下する原因になります。
✅️その結果、腎臓のSOSサインの指標になる、「タンパク尿」が出始めます。
✅️この、「タンパク尿」を放って置くと、将来「人工透析」が必要になるリスクが高まります。
血圧が低すぎるとどうなる?
✅️血圧が低いと腎臓への血流が不足し、必要な「ろ過」ができなくなる可能性があります。
✅️特に注意したいのが、
・降圧剤を強く効かせすぎている場合
・脱水状態(発熱、下痢、夏場の水分不足)
・動脈硬化が進んでる場合
✅️めまい・ふらつき・だるさが出る時は、血圧が下がり過ぎの可能性があります。
腎臓を守る「ちょうどいい血圧」
✅️一般的な目標は、130/80mmHg未満です。
✅️ただし、年齢や病気によって調整が必要です。
・高齢者では、下げすぎによる転倒や腎血流不足を避ける必要がある
・心不全や虚血性心疾患がある人は、急な血圧低下は要注意
・自宅での血圧測定は「朝(起床後1時間以内・服薬前)」と「夜(就寝前)」の2回が目安
・家庭での血圧値の記録を続けて、診察時に医師に見てもらうと薬の調整に役立つ
生活習慣でできる血圧ケア
✅️減塩
加工食品や外食に注意しましょう。味噌汁が「具だくさん・汁少なめ」の工夫
✅️水分補給
腎機能に応じて医師の水分摂取量の指示がない場合は、基本は「脱水は避ける」
✅️体重管理
内臓脂肪を減らすと血圧も安定しやすい
✅️運動
・軽めの有酸素運動が効果的
・激しい運動は血圧変動を招くので注意
✅️睡眠とストレス対策
睡眠不足やストレスは交感神経を高め、血圧上昇につながる
まとめ
腎臓を守るための血圧管理は「高すぎても低すぎてもダメ」です。
目標は「自分に合った適切な血圧」を理解して安定させることです。
日々の測定と記録を続けて、違和感があれば医師に相談しましょう。
腎臓は一度悪くなると、元の機能に戻りにくい臓器です。
今のうちから血圧管理を意識していきましょう。
明日も元気に過ごせますように。
ご精読ありがとうございました。
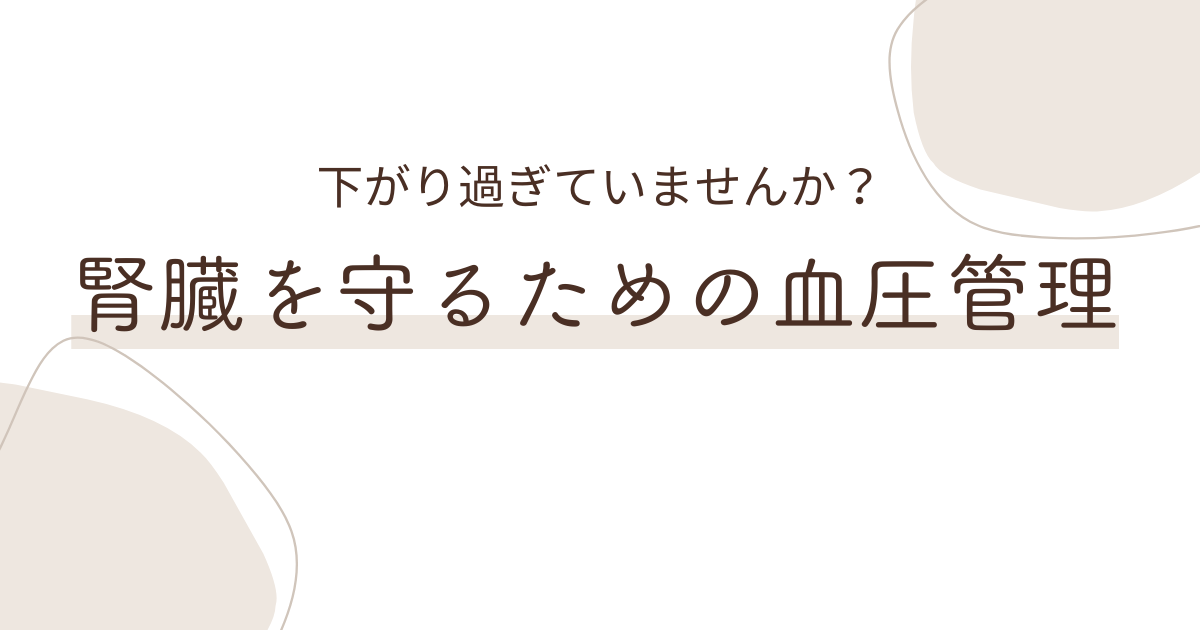

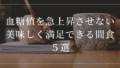
コメント